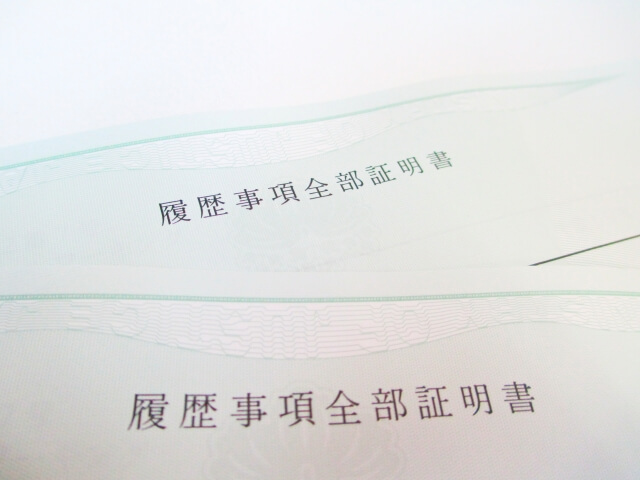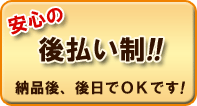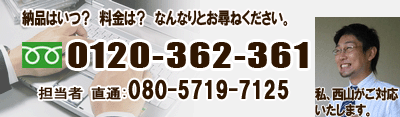写真:ナイアガラの滝
写真:ナイアガラの滝
カナダに観光のために親子で渡航する方を事例として、
戸籍謄本の翻訳から公証、あとはアポスティーユの取得の必要性の有無について共有いたします。
是非ご参考になさってください。
ご相談内容
ハーグ条約があるため、戸籍謄本を英訳したものに公証をもらうのと、あとはアポスティーユをもらう必要があるかどうかで迷っています。
公証役場での公証(法務省)は必要ですが、観光目的ですとアポスティーユ(外務省)まではいらないのではないかなと感じます。
もちろん、あっても困るものではございませんので、取得するのも一考です。
「と感じます」と、ふわっと申し上げましたのは、これらのことをカナダ当局や公証役場に問い合わせても、あまりきちんと教えてもらえなかったり、聞くたびに必要なものが変わったりするためで、この辺が手続きの難しいところです。
少なくとも、公証役場で公証を得る必要があります。
公証役場で公証を得る場合、その英語が日本語と相違ないこと(意図を持って改変せず、日本語のとおりに英語になっていること)が重要になります。なぜなら、日本語と英語で違うことが書かれているものを、公証役場としては公証することができないからです。
このことを公証役場で証明する必要があります。
証明といっても難しい話ではなく、お客様が、「この英語の戸籍謄本は、日本語と相違ない」ことを宣誓した書類を英語の戸籍謄本と一緒に公証役場に提出していただくだけです。
当社の戸籍謄本の翻訳サービスでは、ご希望の方には、この宣誓書(日本語)のひな形を無料でお付けしています。
この宣誓書に、日付とお客様のお名前を記入いただき、ハンコ(認めでOK)を押していただくだけでお使いいただけます。
また、ここでのお話からは逸れますが、宣誓書のほか、翻訳証明(英語。当社が翻訳したという証明)もお付けしますので、宣誓書は公証役場で公証を得るために、翻訳証明は(おそらく使う機会はありませんが、必要であれば)カナダへの入国手続きの際に、それぞれご利用いただけます。
ご参考までに、全国の公証役場一覧を表しているウェブページをご案内させていただきます。
公証役場一覧
http://www.koshonin.gr.jp/list
公証はどの公証役場でもいただけますが、アポスティーユは、取り扱っている公証役場が限定的で、主に都心部の公証役場のみの取り扱いになっていますのでご注意ください。
なお、ここでお話させていただいた内容は、当社の数多くの戸籍謄本の翻訳の経験から分かり得たことで、おそらく正しいとは思いますが、公証役場によっては手続きが異なる場合もございます。
念のため、お手続きについては、お近くの公証役場にお尋ねください。
下記にもご参考いただけるページがあります。ご覧ください。
戸籍謄本 英語に翻訳から公証まで カナダ編
https://www.tiners-p.com/blog/825
戸籍謄本の翻訳サービスはこちら
https://www.tiners-p.com/family-register.html
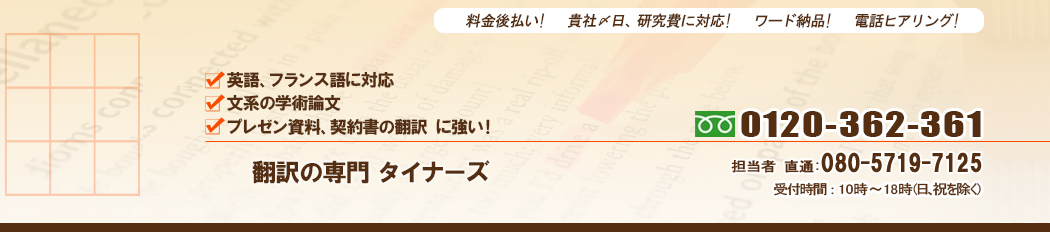 翻訳会社 タイナーズのブログ
翻訳会社 タイナーズのブログ