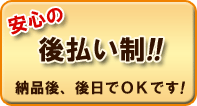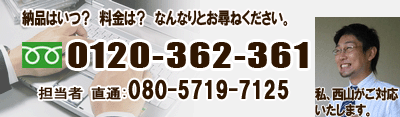さて、このエントリーでは、弊社で翻訳の仕事をしたいとお考えの方向けにお伝えします。
嬉しいことに、
「翻訳の仕事がしたいんです」
と、ご応募をいただく機会がすごく増えてきました。
一緒にお客様の翻訳原稿を作成しながら、
「ここはこの表現のほうがいいんじゃないかな」
「この日本語表現は、もっと練ることができると思う」
などなど、いろいろお話をしながら完成に持っていくのが楽しいんです。
しかし、実際のところ、「翻訳原稿を作成する」という行為は、なかなか難しいものだと思います。
私のこれまでの経験から申し上げますと、弊社で翻訳者として活躍していただくには、以下のものが必要だと思います。
1、言語(英語)能力
2、内容を理解することができる能力(学力あるいは地頭の良さ)
3、表現する力
1、言語(英語)能力 については、
これは分かりやすいですね。
要は、英語をどれだけ操れるか、理解ができるかという言語能力です。
「どこまでの言語能力を持っていれば、翻訳業務に携わることができるのか」、なかなか分かりやすい物差しはないのですが、目安としては、英検では準1級、できれば1級(いずれも一次試験合格で充分です)が望ましく、TOEICですと少なくとも900点以上は必要ではないかと考えています。
TOEICについては、皆さんご存知のように、難解な問題はありませんので(問題数はすごく多いですが 汗)、一定程度以上の言語(英語)能力をお持ちの場合は、普通に900点以上を獲得します。そのため、参考になりづらいというのがあります。
その点、英検については、なんとも難解な(リーディングの)問題が登場しますので、TOEICに比べれば、参考になると考えています。
なお、これはあくまで目安であって、弊社の翻訳者の募集では、これらの資格の有無、点数の高低のみで合否を決めるわけではありません。だって、「資格がある・点数が高い=翻訳者としての適正がある」ということもありませんし、「資格がない・点数が低い=翻訳者としての適正がない」ということもありませんからね。大事なのは、今あなたが弊社が求める翻訳者としての能力を有しているかどうかであって、それは筆記試験で判断しています。
2、内容を理解することができる能力(学力あるいは地頭の良さ)について、
これは英語とは直接関係はなく、要は学力と地頭の良さです。
原文の内容を理解することができるかどうか、つまり、正しくインプットすることができるかどうか、ということですね。
たとえば、英語でおいしいサンドウィッチの作り方が書かれていたとして、たいてい理解できますよね?なぜなら、書かれている内容が簡単だからです。
ですが、たとえば、国際会計基準のレポートだった場合は内容が難しく理解が困難な場合があります。ここで注意しなければならないのは、「国際会計基準のことを知らないから分からない」んじゃないんです。もちろん、どんな方でも知らないことはたくさんありますから、要はそこに書かれていることを自分で調べて、「何のことを言っているのか」「この一文はどういう意味か」を理解するということですね。
理解するためには、どうやら一定程度以上の学力と地頭の良さがいるんじゃないかと思います。
なお、ここで言う地頭の良さというのは、そんなに珍しいものじゃなくて、「なんだかあの子、頭いいよね」というくらいのもので充分です。
3、表現する力について、
これも英語とは関係なく、アウトプットのことを指しています。訳文をどのように表現するかということですね。
同じ原文でも、表現の仕方によってかなりその訳文は変わってきます。
このような違いです。
「私たちは、あなたの会社が行っている業務に関して、帳簿を使うことによって改善する役割を受け持つことができます」
「弊社は、貴社の取り扱い業務について、帳簿を用いて業務改善の役割を果たします」
どちらも同じことを言っていますが、前者はなんだかカクカクしていて、上手くはないですよね。後者のほうが翻訳原稿として適しています。ビジネスシーンで用いられる表現、カッコイイ表現です。
表現する力は、センスの有無によっているのではないかというのが、弊社の見解です。センスというのは、長い年月をかけて現在まで少しずつ少しずつ培ってきたものです。ですから、「こういう勉強をすれば身に付く」というものではなく、たとえば小説を読んだり、手紙を書いてみたり、映画を観たりと、日常の中でゆっくり醸成されていきます。
「得ようと思ってもすぐには得られない」のが表現する力ですので、この力を持っていらっしゃる方は、翻訳業務に携わることのできるかなり高い能力を有していると言えます。
このように3つの力をご説明してきましたが、平たく申し上げますと、
翻訳業務に携わるためには、
1、高い言語(英語)能力を有していることは当然であって、【当然】
2、内容を理解することができる能力が高いほど良くて、【重要】
3、表現する力が高いと、かなり優位性が高い【高いと素晴らしい】
ということになります。
とりわけ、「内容を理解することができる能力」と「表現する力」は、すぐに得られるものではありませんので、その意味で、これらを高い水準をお持ちの方は、翻訳の世界、少なくとも弊社では強く必要とされます。
丁寧にご説明にしますと、このようになりますが、実際、やってみないと分からない場合も多いです。
弊社には、ご自身では1、2、3、が高いのか低いのか分からなくて、実際に翻訳業務に携わってみますと、「ものすごくハイレベルな翻訳原稿が作成できている!」という方も多くいらっしゃいますので、アドバイスとしましては、ご興味をお持ちでしたら、まずはご応募ください。ご自身では気づいていない能力の高さを知ることになると思います。
皆さんウェルカムです。
翻訳業務は、得ることが多く、携わっていて楽しいです。(もちろん大変さもあります)
少しでも「やってみようかな」とお思いでしたら、ぜひ前に進まれることをお勧めします。
弊社にご応募いただいて、いいお返事をさせていただけるかどうかはご応募の段階では分かりませんが、もし晴れて合格となり、一緒にお仕事をする段になりましたら、その節はよろしくお願いいたします!
一緒に翻訳原稿を作成しましょう!
翻訳者の募集ページはこちらです。
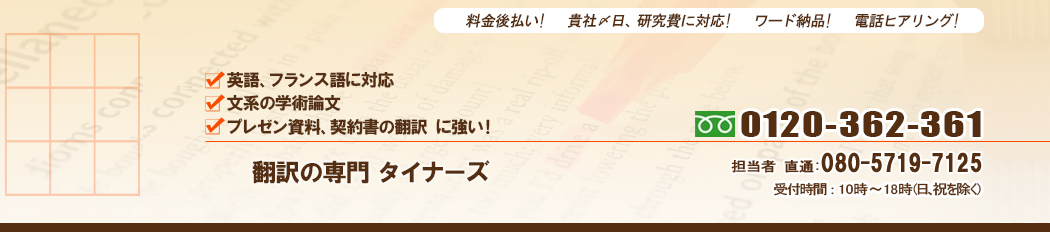 翻訳会社 タイナーズのブログ
翻訳会社 タイナーズのブログ